隣国のレッドカード(資源エネルギー論3)
(2010年筆)
2010年の9月、尖閣諸島に進入した中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突し、日本側が中国人船長を逮捕するという事件が発生しました。日本政府の対応は迷走し、あげくの果てに衝突事件の映像が海保職員によってネット上に流れてしまった経緯は記憶に新しいものと思われます。この事件で明らかになったことは、中国側がその経済力を背景に一連の制裁措置を打ち出したことであり、それは東シナ海ガス田協議の交渉中断・中国人の訪日観光自粛の呼びかけなどですが、中でも日本経済に最も大きな打撃を与えたのがレアメタルの輸入問題でした。中国側は禁輸という声明こそ出していませんが、この問題では既に2009年から”産出するレアメタルを自国の経済発展に使うべきだ”と強く主張していたことから、事実上の禁輸措置と考えてよさそうです。これにより家電メーカーや自動車メーカーを中心に幅広い業種で、生産ラインがストップしたり大幅に遅れを来すなどの重大な影響が生じたのでした。
レアメタルとは、世界的に生産量が少ない31種の金属鉱物の総称であり、鉄や銅に比べて消費量こそ少ないものの、ハイテク製品には欠かせない素材として近年注目を集めているものです。例えばハイブリッド車の駆動モーターはレアアースの一種である「ネオジウム」を使った磁石なしには動かず、鋼材の切削に使う超硬工具は「タングステン」が原料となっています。また液晶テレビの画面には「インジウム」が欠かせず、外枠樹脂には「アンチモニー」が添加されています。そしてこれら4つの鉱物はそのほとんどが中国からの輸入に頼っており、中国からの供給が停止すれば日本のメーカーはたちまち立ちゆかなくなってしまうわけです。
図3‐17 レアメタル価格の推移
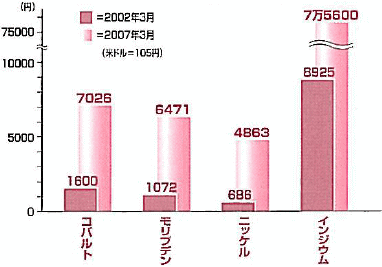
出典:「資源の世界地図」
尖閣事件に際しての中国の対応は、日本の急所を正確に突いた強力なものだったのであり、これを機会に商社やメーカーは調達先を多様化することでリスクを減らさなければならなくなったのでした。しかし、2003年以降レアメタルの価格が高騰を続け(図3-17)、その要因が中国はもとより生産国の国内消費の増大という構造的なものであったことを考えれば、わが国の対応は遅きに失したとも言えるのです。
ことはレアメタルだけではなく、その他の鉱物資源についても同様であり、世界の鉱石メーカーは伸びる一方の需要に対応するため次々と買収合併を繰り返し、鉄・石炭など主要な分野はBHPビリトンやリオ・ティントを始めとする5社に寡占化されつつある状況です。日本の鉱山会社も従来は自前の鉱山を海外に持たず、海外メジャーとのジョィントベンチャーが精一杯というところでした。しかし、「日本に居ながら資金に任せて買い付けてきたやり方はもう通用しない」、リスクを背負っても自らの力で開発・運営を行うべき時代に変わっているのだと申し上げられるのです。
図3‐18 レアメタル価格の推移
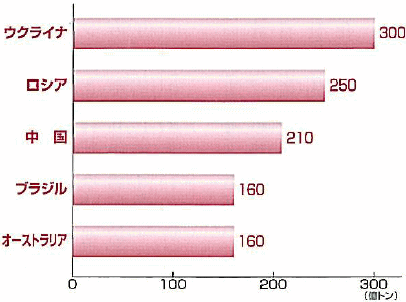
出典:「資源の世界地図」
「鉄鉱石」(図3-18)についても中国の消費量が急増し、2003年から中国は世界最大の鉄鉱石輸入国に転換、これを受けて鉄鋼相場は急騰し品薄感は否めなくなっているようです。
図3‐19 国別のウラン埋蔵量
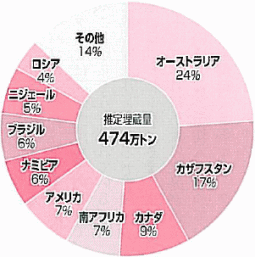
出典:「資源の世界地図」
図3‐20 世界の銅鉱石の生産シェア
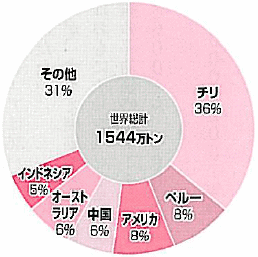
出典:「資源の世界地図」
「ウラン」(図3-19)の価格も急騰していますが、この背景には各国の原発建設計画が着々と進んでいることがあるようです。「銅」に至っては既に需要が供給を上回りつつあり、中印などのインフラ整備がここのまま進めばさらに供給が逼迫するといわれています(図3-20)。
図3‐21 1トン当たりの石炭価格の推移
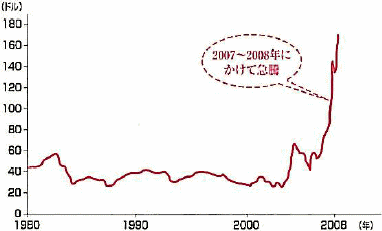
出典:「資源の世界地図」
また「石炭」の最大生産国は中国ですが、中国では国内消費が生産を上回って2007年には鉄同様輸入国となってしまい、最大の輸出国は豪となっています。新興国の需要の伸びが獲得競争を引き起こし、ここでも価格が急騰しています(図3-21)。アルミニウムの原料である「ボーキサイト」にしても事情は同様で、世界の需給バランスは豪のボーキサイト産出量と、中国のアルミ消費量にかかっているといわれています(図3-22)。
図3‐22 世界のボーキサイトの生産量
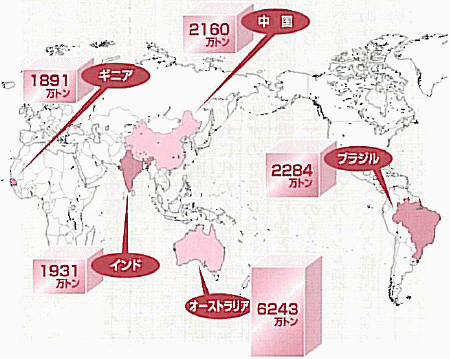
出典:「資源の世界地図」
【参考文献】
世界経済のネタ帳
日本生活習慣病予防協会
日本経済新聞2010年10月24日朝刊
ボルマー&ヴァルムート著「健康と食べ物,あっと驚く常識のウソ」(草思社)
田中平三監修「サプリメント・健康食品の『効き目』と『安全性』」(同文書院)
福岡伸一「生物と無生物の間」(講談社現代新書)
赤祖父俊一「正しく知る地球温暖化」(誠文堂新光社)
オープンコンテントの百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日経電子版2009年11月26日
産経新聞2003年6月22日
【2010年ビルダーバーグ会議・緊急報告】”主役”不在の今年のビルダーバーグ会議。崩壊しつつある”グローバル・ガバナンス”の行方 (1) 2010年6月10日
農林水産省HP
ビジネスのための雑学知ったかぶり「日本の食料自給率は40%」
財団法人エネルギー総合高額研究所HP
シフトムHP
近藤邦明「環境問題を考える」
永濱・鈴木編「[図解]資源の世界地図」(青春出版社)
武田邦彦「温暖化謀略論」(ビジネス社)

